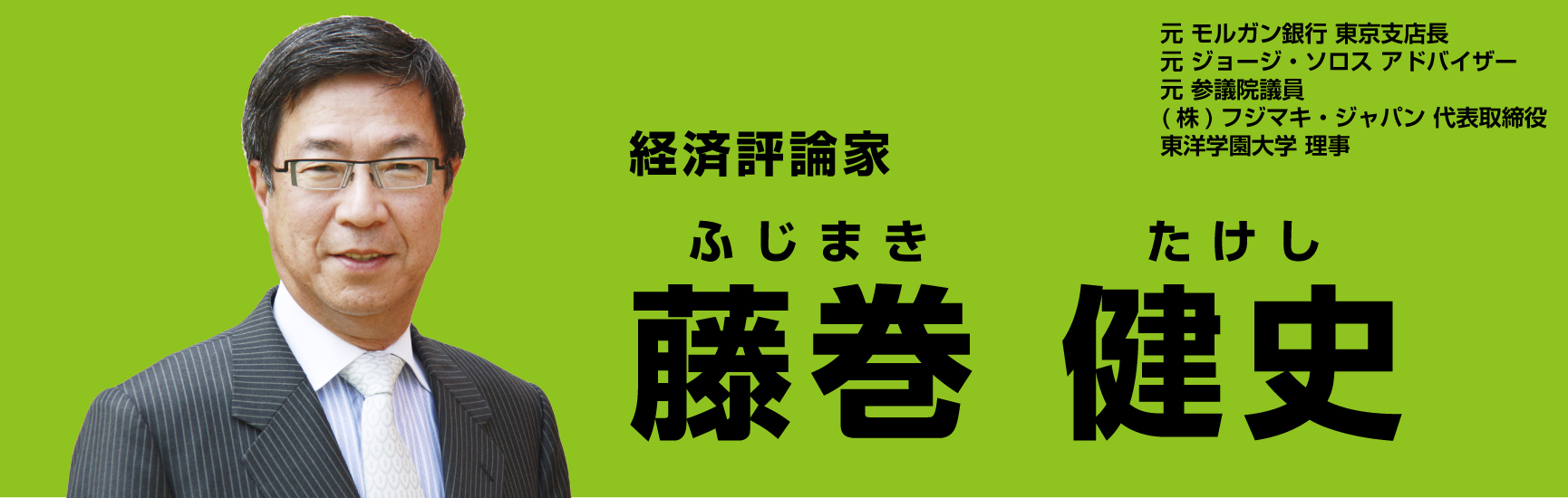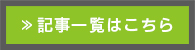1.「ヘミングウェイが見たインフレ」
昨日の大樹小機。「『去年はヘルンベルクに旅館を買えるほどの金を貯めてました。今じゃ、その金でシャンパン4本も買えやしません』。米国の作家、ヘミングウェイが特派員としてドイツに渡り、現地のウエーターの話を記録している」これがまさにハイパーインフレ。この導入部もそうだが、昨日の「大樹小機」は私が著書、SNS,論考で何度も触れたアダム・ファーガソン著「ハイパーインフレの悪夢』」の内容紹介に大半を費やしている。一読に値する。「通貨価値の下落に伴うインフレが市民の生活を苦しめ、社会の不安が高まった。(略)やっとインフレを止めたのは土地などを担保にした新通貨レンテンマルクの発行だ」。
ペンネーム赤金氏は「1920年代のドイツの惨状と今とをそのまま比べられるものではない。ただ異国の遠い昔話だと切り捨てきれないものがある」と論考を締めているが、そのあたりが(日本の新聞に)載せられるぎりぎりの主張だろう。私は「1920年代のドイツの惨状そのままが、今、目前に迫っていると思っている。日銀の財務内容から判断して、である。放漫経済の放置、日銀の財政ファイナンス(=異次元緩和)による危機先送りのツケで国民は地獄を味わざるを得ない。ちなみに、この記事は「インフレ懸念の時に、長期国債を買うことの愚かさ」をも教えてもくれる。10億円の国債が満期で元本を返してもらったらシャンパン4本も買えない」それでいいのか?ということ。ご存じのように私はドル保有を進めているが、ドルのMMF の様な短期物に限る。わずかな利回り向上のために長期債に手を出すのは愚の骨頂だ。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO78685200S1A221C2EN8000/
2.「 利上げよりもはるかに大きな激震=償還債券の再投資をしない」
昨日発表の米消費支出物価も39年ぶりの高い伸びだった。あらゆる物価指数が39年ぶりの伸びだ。ところで、この記事にも「2022年3月に量的緩和縮小(テーパリング)を終了する」と書いてある。なんども言うが、テーパリングを(量的緩和縮小)と訳すから事実誤認の書き方となる。2022年3月には量的緩和の縮小など「終了」などしない。始まってもいない。2022年3月段階でこそ量的緩和のピークである。FRBのバランスシートが最もでかい(=お金を最大限ばらまいた状態)。 保有資産を減らし始めて、初めて量的緩和の縮小が始まる。その時期はまだFRBは決めていない。保有債券の満期が来て償還されたお金を再投資しないことにより、量的緩和の縮小が始まる。ここから景色がそれまでと180度変わる。この量的緩和からの脱却が利上げよりもはるかに大きな激震となるだろう。その時、きっと、円と日銀は終わる。新しい中央銀行の設立準備に早急に取り掛かるべきだ。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO78726620T21C21A2EP0000/
3.「え、え、コロナ禍での比較的早い景気回復は、金融緩和のせい?」
一昨日、黒田日銀総裁は「コロナ禍での比較的早い景気回復は、金融緩和が大きな役割を果たしてきた」と述べたとのこと。世界で最も過激に金融緩和を行っている日本の景気回復が他国にもっとも遅れているのはどう説明するの?
4.「簿価会計の財務諸表を米系金融機関は信じるか?」
一昨日アップした、私のプレジデントオンラインに記事について池田信夫先生から、反論があった。「いつまでも誤った話を繰り返すのはやめるべきです。日銀の資産評価は取得原価なので『日銀の債務超過』は起こりえない。問題は日銀ではなく民間金融機関(時価評価)の債務超過」
私の反論は以下の通り。
「私が銀行からお金を借りようとしたとき、私の簿価会計で作った財務諸表を銀行が信じて融資をしてくれますか?与信をする方が自分の評価基準で分析し、融資の是非を判断するのです。米系金融機関にとって簿価会計は前世紀の遺物です。時価会計で融資相手を審査(この場合は日銀)します。しかも本日の私の論考は政策金利(短期金利)を引き上げると、「受け取り利息―支払い利息」で損の垂れ流し()負のシニョリッジ」となり債務超過になる、という話でバリバリの簿価会計での話です。
今回の論考には書きませんでしたが、長期金利が上昇すると。日銀は保有国債に莫大な評価損を生じます。これも債務超過になります。こちらは時価評価の話です。日銀が原価法なのでこの評価損を気にしませんと言っても、評価する外資はバリバリに気にしますよ」
https://president.jp/articles/-/53078
5.「日銀保有国債に償却原価法を適用するのは正しいのか?(会計検査院への質問)
池田先生に対する私の反論に対し、他の方から以下の反応が来た。「FRSも米国基準も満期保有目的債券の評価は償却原価法です。金利上昇による価格の下落は回復します。だからこそ金融商品会計に関する実務指針でも減損処理を強制しておりません」
私の反論は以下の通り。
「債券は満期に元本に戻るから原価でいいなどという人は米国にはいません。その時点で、その企業が倒産するか否かを判断するのは、その時いくらで保有資産を売却し現金化できるか(=時価会計)です。保有債の満期まで企業が倒産回避できるなどという保証はどこにもない。
それに日銀が簿価会計をしているとは「満期まで長期債を保有しない(=インフレになっても売りオペをしない≒バランスシートの規模を縮小しない=世の中にお金ジャブジャブ)ということになります。金融調節の放棄宣言です。
そもそも日銀が国債保有に簿価会計を決めた時(1990年代後半)、日銀は民間金融機関と同じ会計処理(=満期保有は償却原価法、途中売却の可能性のある者は時価評価)を採用すると公表しました。当時の日銀は3か月未満の短期債しか買っていませんでしたから、満期保有≒簿価会計は許容できるものでした。しかし異次元緩和以降の保有国債はほとんどが長期国債です。インフレになれば金融引き締めをしなくてはいけません。売りオペをしなくてはいけないのです(もっとも今の黒田日銀はそれをやったら財政破綻&日銀の破綻で、出来ませんが=出口が無い)。従って満期保有を意図していたもののはずがありません。本来の会計の趣旨からすれば、長期債の爆買いをした段階で、時価評価に変えねばならなかったのです。日銀の監督官庁である会計検査院に(長期債補油を開始祖宝には)日銀の会計基準を変えるのが筋では?質問するつもりでしたが落選してしまって、質問できませんでした。