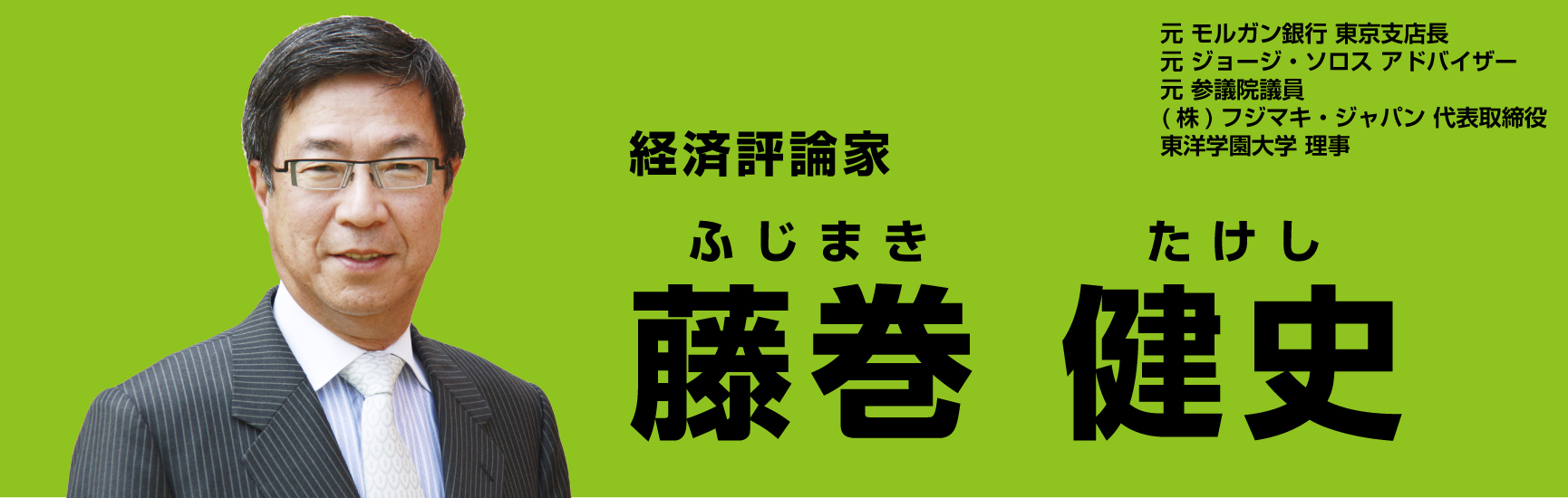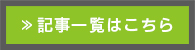1.「年金の持続性と財政の持続性は両立しない」
昨日の日経新聞1面トップ記事は「企業年金の積み立て不足解消へ 金利上昇で充足率97%、賃上げ後押し」
一見、日本国民が喜びそうな記事。しかし現実は違う。
私が国会で何度も質問したように「財政の持続性」と「年金の持続性」は学問上両立しない。どちらが持続可能になれば、どちらかが破綻する。
この記事にある通り年金財務の改善は長期期金利上昇が理由だ。年金はスプレッドが大きい(r>g)ほど、年金財政が改善し、持続税が高まる。
「r」は長期金利で「g」は経済成長率だ、この記事にある通り年金財務の改善は長期期金利上昇が理由だ。運用利回りが年金掛け金(gに依存する)の上昇より大きいから、と考えればよい。5年ごとの年金検証は、そのスプレッドの大きさに分けて5年後ごとの年金財政の健全性(=年金の持続性)を提示している。
一方、(国の)財政の持続性は、プライマリーバランス達成後にr<gならば借金が額が縮小していくので持続可能である。国債金利の支払いよりも税収が大きい(税収は経済成長率に依存するからだ)ほど、財政の持続性が増す。r>gならば財政派はランである。
すなわち、今日のニュースのように長期金利が上昇していくと、年金の健全性は増すが、財政破綻の危険性は高まるのだ。
日銀が国債を買い取っている以上、普通は資金繰り倒産の可能性は低く(CDSレートが低い理由)財政破綻の確率はごく低いはずだが、そうは言っていられなくなる日があるのかもしれない。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG2934U0Z20C25A9000000/
2,「売却に113年もかかるような(株ETFの)買い入れの副作用を軽視してはならない」
元日銀理事の山本謙三さんが11月4日に以下の論考をご自身のホームページにアップされた。翌日(=昨日)、日経平均の大幅下げがあったのだから、なんとも絶妙(?)なタイミングイだった。(そんなことはどうでもいいのだが)
必読の論考だ。
「山本さん曰く
(日銀の保有株ETFの処分計画によれば)保有残高がゼロになるには実に113年かかる計算だ。
日銀は、この処分計画を「市場への攪乱的な影響を回避する」方針に基づく決定と説明する。
市場への攪乱的な影響を避けるのに113年かかる規模のETFを、異次元緩和ではわずか11年で買い入れた。これは、ETFの買い入れが市場に著しく攪乱的な影響を与えたことの証明にほかならない」
「株価の形成は、市場経済の根幹にかかわる。売却に113年もかかるような買い入れの副作用を軽視してはならない」
「異次元緩和期間中のETF買い入れは、中央銀行として望ましくないものであったことを率直に認め、ETFや株式の買い入れは、よほどの金融ショック時を除き行ってはならないことを明確にすべきではないか。
113年後といえば、私たちのほとんどが生きていない。それほどの時間をかけざるをえなくなったことの意味を真摯に受け止め、次の世代に語り継がなければならない」
- 「
朝日新聞原編集委員の10月31日の記事。
原編集委員の記事にあるこの表とその解説が、まさに「今の日銀の金融政策の矛盾」を端的に表す。
原編集委員曰く「主要中央銀行の「実質金利」(政策金利から9月の消費者物価指数の前年同月比上昇率を引いた値)のグラフを見てほしい。
日銀はマイナス2.4%と主要中銀の中でひとり大幅なマイナス(緩和)だ。これは『物価を抑える』政策ではなく、『物価を上げる』ための金利水準になっていることを意味する」。
そして、以下の文章でまとめていらっしゃる。
「白川方明・元日銀総裁が著書「中央銀行 セントラルバンカーの経験した39年」の中でこういう趣旨のことを書いている。
国民から「中央銀行は頑固だが長い目で見て経済の安定に必要なことをしてくれているのだろう」という信頼を得ていなければ、民主主義社会の中で存立することは難しい。中央銀行という組織も、それを代表する総裁も、社会からの「共感」を得ることが不可欠――。
信ずる政策を頑固に批判を恐れず。そういう営みの積み重ねによってこそ、国民の信頼を得た強い中央銀行が生まれるのではないだろうか」
まさにすばらしい言葉を伊紹介してくださっている。
https://www.asahi.com/articles/ASTBZ4GBFTBZUQIP01DM.html?iref=pc_ss_date_article
4.「経済財政諮問会議の民間議員に垣間見える政府の本音」
わ〜.黒田さんを熱心に支えた若田部元日銀副総裁と永浜さん、こりゃ建前がどうであれ、財政出動政府だな。インフレを公約し実施手段を整えたと思ったらば、その軍師まで、その方向の人材で固めたのか。
上の文章で、①インフレを公約したとは「借金総額の対GDP比を低減するのを目標とする」としたこと(インフレ加速しかこれを達成する方法は考えつかない,他の方法は理論的には可能だが、今の日本では現実的に無理)②実施手段を整えたとは「減税.ばらまき政策」&「日銀が異常ともいえる実質低金利を継続」していること,そして③ついに軍師までリフレ派で固めたこと。 これではハイパインフレに向けて一直線。究極の再生再建ができるが、国民生活は地獄。長期金利暴騰、円は1ドル1兆円(=紙屑化)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA05A2J0V01C25A1000000/
年金の持続性と財政の持続性は両立しない」