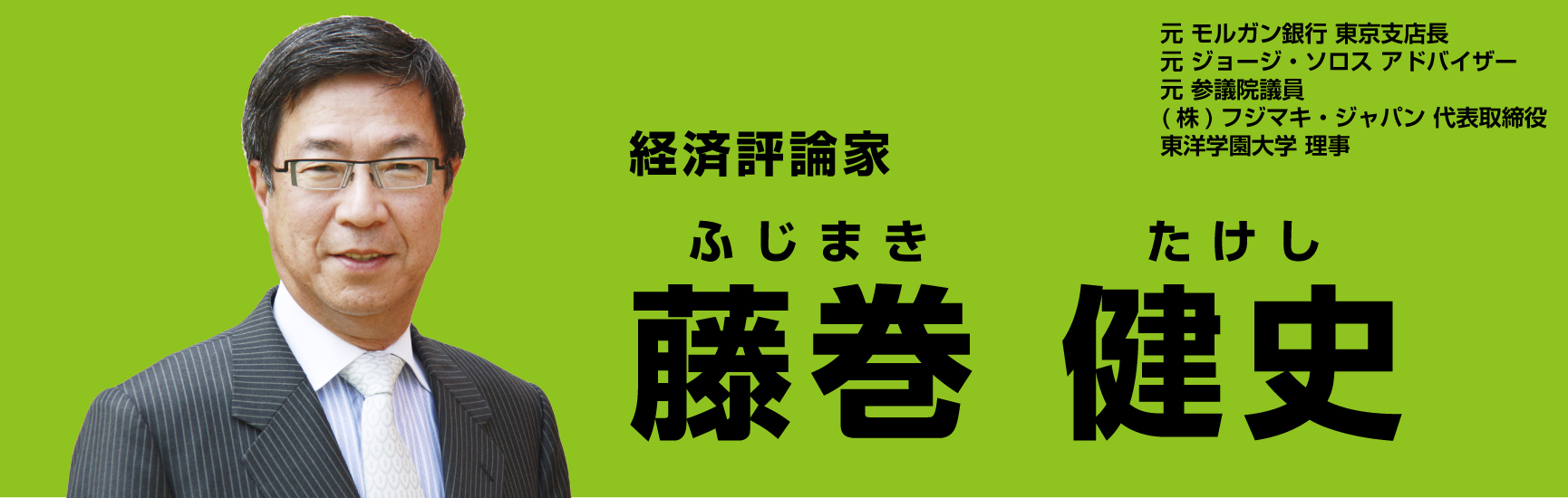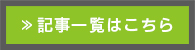(ここに述べる意見/分析は日本維新の会の公式見解でも分析でもありません
私の個人的見解・分析であることをご理解ください)
1.「インフレ税増税への道へまっしぐら」
政府も家計も借金は返さなければならないとは同じ。違いは国家には徴税権という合法的な借金返済の法があるが家計にはない点。日本は莫大な借金があるのに2番目に大きな税収能力のある所得税の減税をしてしまった。これで最も徴税能力のある消費税を減税したら、徴税能力のあるのは、インフレ税(物価高騰)しかなくなる。その方向に日本はまっしぐらと突き進んでいるようだ。
元来政治家は目に見得る税金を増税すると選挙で落ちるから、目に見えず非難されにくいインフレ税を選択しがち。
結果、消費税は無くなったが、米1㌔100万円の世界が到来する。これは消費減税を主張する低所得者層には壊滅的に厳しい。だから私は自身の首を絞めるような主張はやめた方が賢明と言っている。ジリ貧を抜けようとしてドカ貧を選択することはない。
2,「インフレ税強化に向かっている現実」
日銀は国債を買い紙幣を刷りまくっている。モノやサービスと同じで供給過多になればその価値は落ちる。円の価値の希薄化。それが、現在、世界で最も高い物価上昇であり円安の理由。
しかも今までのバラマキと財政規律の無視で日銀財務は臨界点をすでに超えている。政策金利を現在の0.5%からさらに上げれば、通貨発行”損”が生じ始める。インフレが加速すれば、その通貨発行“損”は加速化する。
更に、日銀は伝統的金融論で買ってはいけないとされる長期国債を爆買いした結果(=財政ファイナンス)その評価損は既に30兆円近く(1.33%で)。長期金利が上昇すればとんでもないスピードで(0.1%上昇で3兆円)評価損は拡大する。この評価損は将来起こる通貨発行“損”の現在割引価値ともいえる。
植田総裁は、「債務超過になっても通貨発行益があるから債務超過は一時的で問題ない」とおっしゃるが(自分ではそうではないことを12分にご存じのはず)。
受取利息が年間1.5兆円ぽっちの通貨発行益では累積した通貨発行損を何年かかって解消できるのか?そんな中央銀行、そしてその発行する通貨など世界中の人たちは信用しない。まさに先に述べたインフレ税どころかハイパーインフレ税への道に突き進んでいるが、政府は究極の財政再建を達成する、しかし国民生活は地獄。
3.「本当に米国は「自由貿易「盟主」降りる」つもりなのか?」
26日の日経新聞1面トップ記事。私は前から言っているようにこの分析に極めて違和感を感じる。
保護貿易に走るつもりなら10%に加え25%の上乗せ関税を継続し、各国との交渉をしない。90日間の停止をして、その間に各国と交渉しようとしているのだ。
最終的に多くの国が米国の要求に屈し、米国とは相互無関税貿易社会が成立する。問答無用のTPP。交渉でTPPを成立させようとすると各国とも、保護すべき国内産業の取り扱いに苦労し、なかなか相互無関税貿易など存在しない。
最終的に米国は他国会社の子会社を米国内に呼び込み、世界的な非関税貿易社会を成立さえドルの基軸通貨としての地位を確立させ、(MAGA=Make America great again)を達成するだろう。
それを理解せずに「保護貿易非難」とかで時間を浪費し、(のちの交渉国との交渉モデルになるよう)最初の交渉相手に日本を選んだのに歩みよる姿勢を見せないととんでもないしっぺ返しを食らうことになるだろう。金融という人間で言えば血流に当たる金融システムが世界最軟弱な状態なのだから、歩み寄りを見せなければ、その時点で日本経済は終わるだろう。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO88317140W5A420C2MM8000/
4. 「トランプ関税は日本にとってマイナスばかりか?」
これを機にコメ農家への保護主義が崩れ、自由競争の世界になれば(会社組織の大規模農業が許可されるなど)米価は安くなり世界と競争ができるきっかけになりうる。
昔、護送船団方式(銀行たるもの一行ともつぶさないとの大蔵省の政策)がとられたがゆえに日本の金融が欧米金融機関にはるかに遅れ、当時、世界との競争にされていたトヨタやソニーが躍進した。規制緩和が有効な理由、なにせ、日本は政治家がだらしなくて外圧が無いと変われない国なのだから。