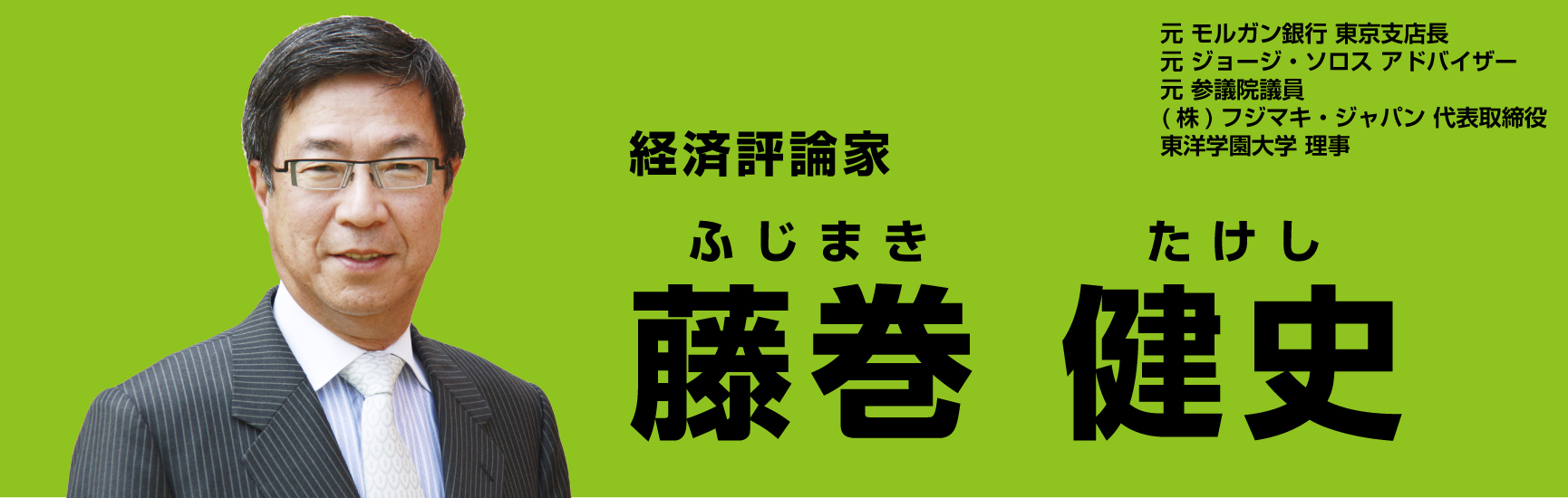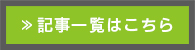1.「とことん追いつめれて日銀が滅茶苦茶な政策発表」
今朝の日経新聞1面記事。「日銀府が来年4月から国債購入の減額圧縮を始める」とのこと。
日経新聞にさらっと書いた、というか、マーケットへの衝撃を抑えるために日銀がさらっと事前公告したのか知らないが、とんでもないニュースだ。
ついに日銀自身がこれ以上の超長期金利上昇に耐えられず、やむを得ず超長期金利の上昇を抑えにかかるという話。
しかし、その見返りとして起こる円安の加速、物価上昇を何とか抑えたいという事前準備だが、それは二つの相反するゴールである。日銀がとことん追いつめれているとの証左でもある。
物価上昇期には金利を上げるのが金融の常識だが、日銀は国債購入の減額圧縮をして(=購入額の増加)、金利を押し下げ物価上昇を加速させ、円安も加速させようというわけだ。それはまわりまわって超長期債の金利を押し上げることにもなる。
昨年国債購入の減額圧縮を決めた際、マーケットでは、減額通りに進められなくなれば、円安が加速してしまうとの予想が圧倒的だった。まさにその事態を迎えるということ。
「国債購入を減額する」とは「通貨の回収を減速する」という意味だ。他国中央銀行に比べて格段に遅いペースの通貨回収を更に送らせようとすること。世の中にお金ジャブジョブ状態が超長期に続くことになるから、物価上昇はとことん加速するだろう。通貨価値の棄損(=インフレ)を抑える術を日銀は無くしたどころか加速させようとしている。中央銀行の交換が不可欠なのが明白になってきた。円の紙くず化を意味する。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO89375290V10C25A6MM8000/
2.「これ以上、超長期金利が上昇すると日銀が窮地に追いやられる理由」
日本国債40年債の利回りは、5年前はおおよそ0.5%だったが今や3.067%。ならば5年前に購入した40年債の価格は半額近くに下落しているはずだ。30年債も情況はそうは変わらない。
これ以上価格が下落(=金利上昇)するとそれらの債券は減損会計を強いられる。時価評価をして損失を損益計算上に計上しなければならなくなるということ。
生保が減損会計を強いられるのなら日銀も減損会計を強いられる。いくら日銀は償却原価法を採用しているから時価会計は関係ないと植田総裁が強弁しても減損会計を強いられるのなら簿価会計でも債務超過の発生だ。損益計算書もとんでもない赤字となり、世界中から日銀が見放される可能性もある。。
1998年に定められた日銀の会計基準は第3条に「当銀行の会計処理は、中央銀行としての財務の健全性を踏まえつつ、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を尊重して行うものとする」とある。「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を尊重」しなければならないのなら生保が減損会計を強いられるのなら日銀も強いられるということ。
生保に減損会計を回避させたり、生保には減損会計を強いるが日銀には強いないなどとうるのは世界中に日銀の苦境をアナウンスするようなもの。市場は容赦はしない。
どれほど円下落、物価上昇のリスクがあろうとも超長期債の相場を下支え(=長期金利の上昇防止)は日銀にとってMustなのだ。それも会計年度が近づき減損会計を強いられる直前の下支えが必要、だ。日銀は苦境に立っている。バラまきと財政ファイナンスのツケはあまりにでかい。
3.「金利上昇期にますます脆弱になる日本の財政」
超長期金利の上昇を抑えるには、日銀が購入し、財務省が超長期債の発行を減少させなければならない。財務省が超長期債の発行を減少させれば、かわりにより短い年限の国債を増発せねばならない。
皆さんが今後の金利上昇を予想するならば、固定金利で借りていた住宅ローンを短期の変動型に変えるなどというバカなことはしないだろう。そんなことをしたら金利が上昇していく際に個人破産を心配して夜も眠らなくなる。借金は金利が安いうちになるべく長期に借りて支払金利額を固定化するのが常識的行為だ。
超長期債を減額し短期債の発行に切り替えるのは、国にとってもアホな行為で国益に反するのだ。