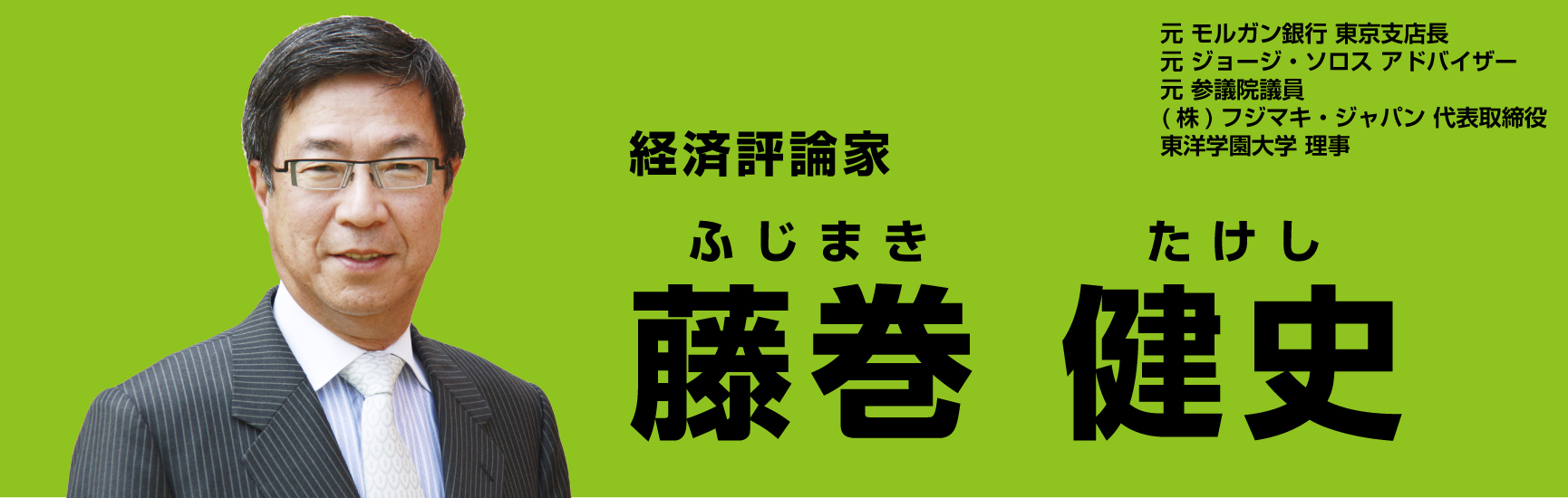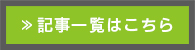1,「ひろゆきさん、ありがとう」
昨日、世間に非常に影響力のある「ひろゆき」さんが、私の「参議院議員任期満了」とのXでのツイートに反応してくださった。ありがとうございます。
ひろゆきさんいわく「『日本国債を刷ってれば、いくらでもお金を使い続けられる』という世迷言をいう政党が出てる昨今。 JPモルガン日本代表の経歴がある金融のガチ専門家の国会議員が減っちゃうのは良くないよなぁ、、と」
2,「経済学ではインフレをインフレ税という。これを翻訳すると」
本日、私のXに以下の リツイートが来た。
「>経済学ではインフレ税とも言われている。ハイパーインフレは大増税と同じで、究極の財政再建。だから政府は安心。しかし国民生活は地獄。――>これを高校生でもわかるように翻訳したら良いんだよね」
以下のように回答した。
「個人タクシーの運転手さんが1000万円銀行から借りる(債務者)と、元利金を返すのが大変。しかしハイパーインフレが来てタクシー初乗りが100万円になると、10人乗せれば1日で銀行に借金を返済できる。大喜び。一方、汗水たらして10年間で1000万円貯めた人(債権者)はタクシー10回乗ったらパーで涙。 すなわちインフレは債権者から債務者への富の実質的な移管。日本の債権者は預金をたくさん持っている国民。日本最大の借金王(債務者)は国。 インフレは国民から国への実質的な富の移管。その点で税金と同じ。だから経済学ではインフレ税という。ハイパーインフレはその程度がすごいから大増税と同じ。タクシー1兆円になれば1323兆円の国の借金など国にとってゴミみたいなもの。タクシー1人乗れば1000億円の消費税が入ってくるし。 だからハイパーインフレは究極の財政再建。しかし国民にとっては地獄。給料や年金は毎月上がるかもしれないが、パンは1時間ごとに上がる。給料もらって1日か2日はパンが買えるかもしれないが、3日目から飢え死にしてしまう。ちなみに1923年のドイツでは1月にタクシー初乗りが700円だったものが12月には1兆1000億円。」
3,「市中にお金が溢れかえっているのか?」
本日、私のXに以下の リツイートが来た。
「そんだけお金が溢れかえっているのなら、庶民は何故金がないの? その金、誰が持ってるのだ?(あなた達じゃないの?) そもそもそんなにお金が溢れているのならもっと景気がよく、お金が回っているはず。 そしてインフレ=悪ではない。ちゃんと庶民にお金が回れば問題ない。 健全なインフレになって困るのは資産を持っているあなた達でしょ?」
以下のように回答した。
「何を言っているのやら?お金が溢れかえっているから、お金の価値が棄損して、物価上昇が続いてるし、これからは、さらにものすごい物価上昇が続くのです。給料や年金の上昇以上に物価があがっているのだから、庶民にお金がなくなるのは当然の現象でしょう」
4.「いまの物価高は、いわば『日銀インフレ』」
昨日の日銀総裁記者会見を受けての朝日新聞・原真人編集委員の記事。是非、読まれて日銀の問題点を把握してください。
原編集委員曰く「日本銀行など各国の中央銀行は『物価の番人』とも呼ばれる。歴史的にも国民生活を圧迫するインフレを抑えることは中央銀行の最大の任務だからだ。なかでも自国通貨、日本でいえば「円」の価値を守ることで物価を安定させること。それは中央銀行にとって欠かせない大きな使命だ。
だがいま、日銀がその使命を果たしているとは言いがたい」。
「こうなったら、ふつうの中央銀行なら政策金利を引き上げるところだ。金融を引き締めて『物価を下げる』政策を採るのが常道である。ところが日銀が現実にやっていることはまったく逆だ。政策金利を極めて低い水準にとどめ、『物価を上げる』政策を続けている。 いまの物価高は、いわば「日銀インフレ」と言ってもいい」
「この5年間で通貨円はあらゆる主要通貨のなかで最も安くなった。円の『ひとり負け』である。それが日本の物価を押し上げ、外国人観光客に高級レストランや高級ホテルを席巻され、日本の1人当たりGDPのランキング順位を押し下げている最大の要因だ。 植田総裁は『今の金融政策は2%インフレ目標を実現するために必要だ』と言う。だとすれば、その目標の実現の代償はあまりにも大きすぎないだろうか」
https://www.asahi.com/articles/AST704GB2T70ULFA02HM.html?iref=pc_ss_date_article
5.「以下の文章で始まる山本謙三元日銀理事の論考」
以下の文章で始まる本日アップされた山本謙三元日銀理事の論考。山本さんは、私同様「日銀は、盛んに利上げに前向きな姿勢を打ち出しているが、実態は、利上げを意図的に遅らせる戦略をとっている」とみていらっしゃる方だ、
山本謙三さん論考で曰く、「最近、日本銀行が主張する『基調的な物価上昇率』に対して、多くの疑問の声が聞かれるようになった。日銀は「『基調的な物価上昇率』がまだ物価目標に達していない」と主張しているが、実際の消費者物価は3年以上にわたり高騰が続いている。このため、「日銀には国民生活の実態が見えていないのではないか」との声である。
これまで日銀は、『基調的な物価上昇率』の定義を状況に応じ変えてきた。さらに、最近はその定義を必ずしも明確にしていない。
にもかかわらず、政策金利を低水準に据え置く最大の根拠を「基調的な物価上昇率」の動きとする。これでは、国民との対話は難しい」
6,「金利を上げたくても上げられない」
原真人朝日新聞編集委員や山本謙三元日銀の論考にあるように、日銀は超緩和政策に固着している。同じような疑問や非難の声が我々以外からもやっと上がり始めてきた。それでも何故、日銀が超金融緩和に固着するのか?
緩和解除したくても、出来ないからだと、どうしてマスコミはまだ理解できないのだろう?
金融緩和を解除すれば日銀が巨大債務超過に陥り、日銀と円の信用がズタズタになるからだ。弱小金融機関も危なくなり金融システムリスクが生じてしまうからでもある。
政策決定会合後の日銀総裁記者会見をここしばらく毎回WEB で見ているが、記者のトンチンカンで的を外した質問ばかりに辟易する。