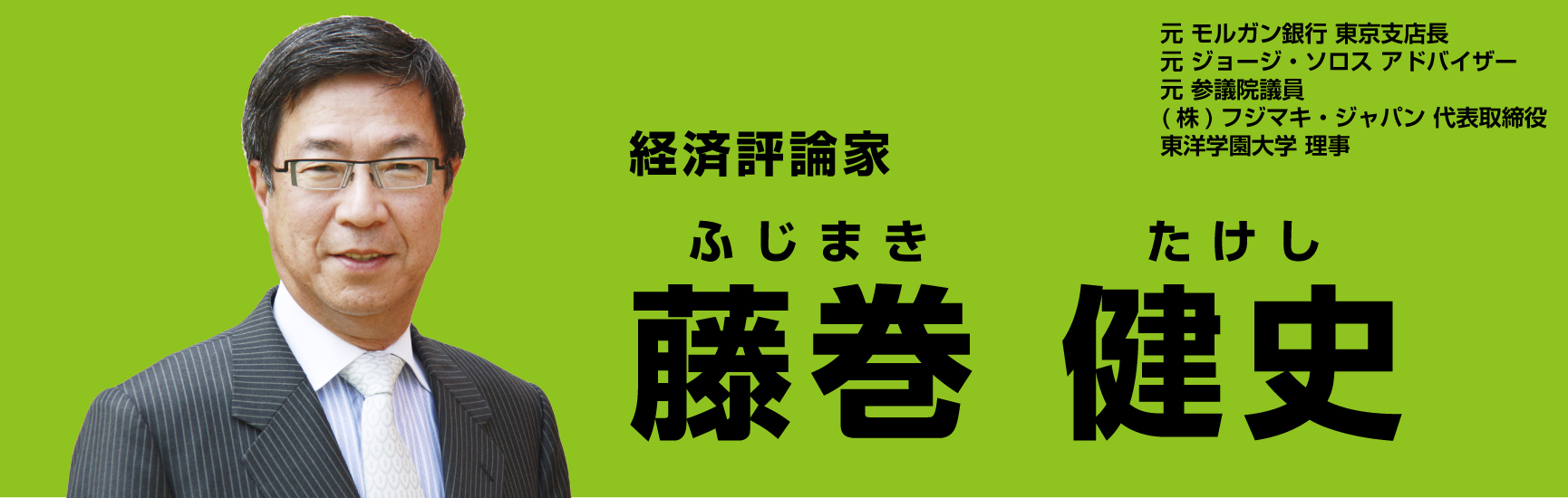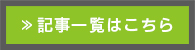1.「『岩盤物価』も動いた、都心の家賃9年で2割弱高 経財白書が分析」
昨日の日経新聞では2025度の年次経済財政報告(経済財政白書)を取り上げている。いわく「家賃は動きにくい『岩盤物価』の一つとされる」「岩盤価格も動くことで、インフレは継続的なものになると予想できる」
――>今の日銀は、私など見たことのない実質金利の低さで物価上昇を後押ししているし、全部の与野党が減税、給付金と物価上昇加速政策(=のどが渇いた海の漂流者に海水を飲ませる政策)を主張している。
それなのに、物価の番人・日銀は物価上昇の抑制手段を既に失っている。過剰流動性を吸収すれば長期金利は急騰し株価は下落し、政策金利を引き上げれば損の垂れ流しが始まってしまうからだ。物価上昇がすさまじいものになっても金融緩和を日銀が継続せざるを得ないと、世界が認識すれば円の信用など吹っ飛んでしまう。誰も円など欲しがらなくなる。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA319HR0R30C25A7000000/
2.「日本の経済・財政、危険水域へ」
本日の日経新聞「大機小機」。タイトルは「日本の経済・財政、危険水域へ」。
いわく「選挙では与野党こぞって「物価高対策」を掲げた。そもそもそうした対策など必要にならないようにするはずの「物価の番人」日本銀行は、「基調的な」物価上昇はいまだ目標とする2%に届かない(インフレが足りない?)と言うばかりである」「消費税をなくして社会保障を維持するとなれば、赤字国債に頼るしかない。7月下旬に示された26年度概算要求基準でも、小泉純一郎内閣以来続いた既存経費の削減を不要とし、20%増額だけを認めた。日本の経済・財政は危険水域に入りつつある」――>危険水域の域に入ってからではもう遅い。危険水域に入らないように進路変更しなければならなかった(=財政規律の重視)のに、日本丸は全速力で危険水域に津混んでいった。ここに至っては早く救命ボートに乗り込んで(=ドルを買う)、沈むゆく泥船から逃げ出すことが必須である。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO90460690U5A800C2DTD000/
3.「『1ドル200円でに品経済の夜は明ける(2002年)』は政策提言本」
昨晩、以下のリツイートが私のXに来た。
「みんな2002年から夜明け待ち なんと言ってもベストセラー! 先生いつ夜はあけるのでしょう?
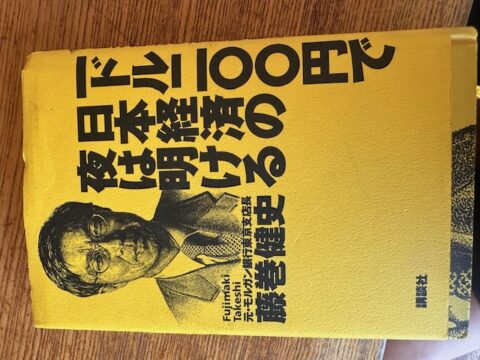 以下のように回答した。
以下のように回答した。
「この本を書いた2002年にこの本で提案した通りのことをやっていていたら円安進行で日本経済は大回復。今頃は経済回復をもとに1ドル200円から円高方向へ向かっていただろうにと残念でなりません。この本では、日本の財政は急速に悪化しており早く円安で日本経済を回復させておかないと財政悪化による悪い長期金利利上昇が始まり、日本は為すすべを失ってしまうと書いたのです。 まさに現実はその懸念通りになりつつあります。 この本では国力に比して強すぎる円の是正方法として、日本政府による短期ドル建て債発行の提案もしています。日本政府は短期ドル建て債で集めたドルを円に変えて歳出に当てる。満期に合わせた為替予約も行い円調達同様の低金利の資金を得る。一方、このドル建て国債を買う国民は為替ヘッジなどできないからドル高が進むだろうと説いたのです。 ところがいろいろな提案を政府は無視するどころか、財政赤字を拡大するばらまき政策をとるとともに禁じ手中の禁じ手である財政ファイナンスまで始めてしまったのです。もうこれではなすすべがありません。 なお読んでみればすぐお分かりのように、この本は日本経済を回復させるために財政赤字がさらに悪化する前に1ドル200円に持っていけ、そしてその方法を書いた政策提言の本であり、1ドルが200円になると予想する予想本ではありません、読解力が皆無の人か、題名だけを見て、今も1ドル200円になっていないのではないかと批判する人が、いますが、私の提案を何一つ採用していないのですから今200円になっておらず、日本が危機に面しているのも当たり前。良い1ドル200円を目指さなかったが故に、とんでもなく悪い1ドル200円を通過して、1ドル500円から1ドル1兆円(=円が法定通貨でなくなる)まで今日本は1直線に歩みつつあるのです」
4.「著名な米国の学者でも日本の事情など全く知らない」
以下のようなリツイートを私のX にいただいた。
「でも調べてみると、2017年以クルーグマン、スティグリッツの両氏ともアベノミクス支持の発言はほとんどありません。(聞かれれば否定はしないようですが)。10年以上前の考えを根拠に自説を強硬に主張されている方々を見るといやでも知の停滞を感じてしまいます。
以下のように返信した。
「おっしゃる通りだと思います。 著名な米国の学者でも日本の事情など全く知らないし、彼らは日本に興味などない(JAPAN AS NO1 が出た時代はそれなりに勉強していたが)。モルガン銀行支店長時代、著名学者やヘッジファンドオーナーはほぼ必ずと言っていいほど、私の支店長室をたずねて来て、日本経済や金融情勢についての講義を受けていった。そして翌日、下手な私の英語をきちんとした英語に直して発表していた。その経験からして、私は、著名学者の日本についての発言を聞くと、どの日本人の発言の翻訳なのかな?と考えることしかしない」
。