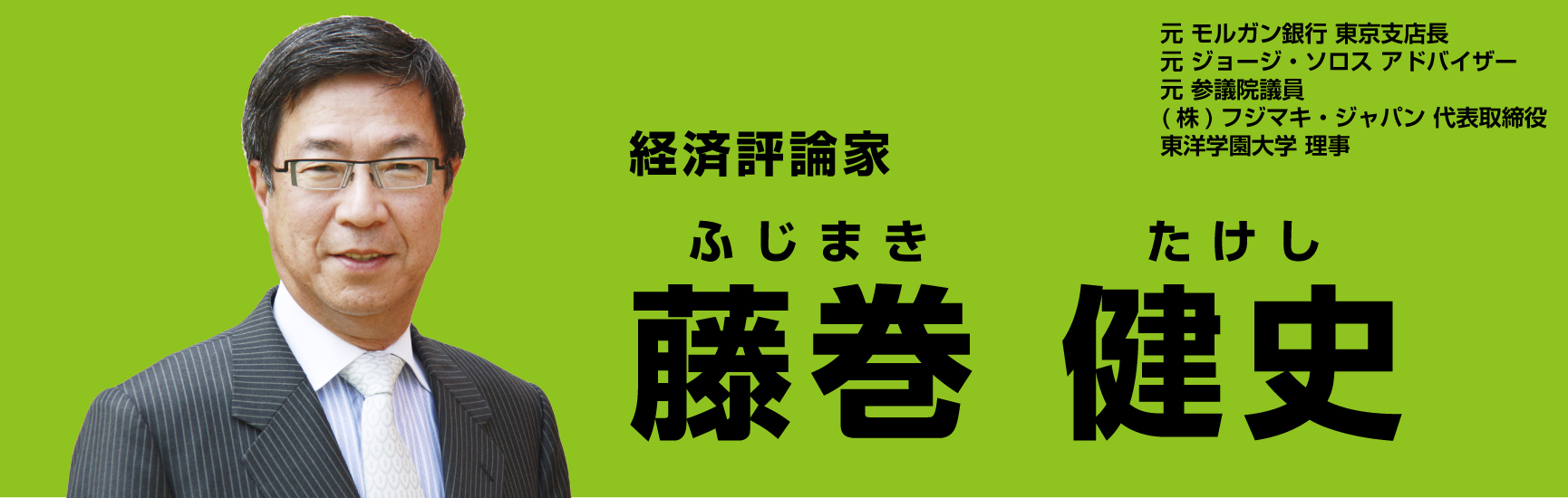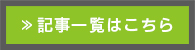1,「日本は景気が良くなったらおしまい」
10年近く前から、私は、逆説的だが、日本は景気が良くなったらお終いといってきた。8月15日朝発表の実質GDPが高かったということでいよいよ、その予想に近づいてきた。景気がよければ物価高は加速する。株などの資産価格が上昇すれば資産効果(株や不動産を持っている人が金持ちになったつもりで消費を増やす。それを見て株価がさらに上がる)で景気は過熱していく。長期金利がさらに上がれば日銀保有国債の評価損は莫大なものになる。0.5%の政策金利をこれ以上上げると日銀の損の垂れ流しがはじまる。したがって日銀は金利は上げられない。一かバチであげてもあと0.25%だろう。物価がどんどん上昇していくのに、日銀は動けない。なぜだの声が世界中からわきあがり日銀の惨状が世界に知れ渡り日銀と円の信用が地に落ちる。
2、「トランプ関税に伴う80兆円米国投資で1ドル200円か?」
昨日の日記新聞朝刊記事.「頭もたげるドル最強説 侮れない『直接投資80兆円』」。
私が関税問題解決の際、つぶやいていたことをマーケットもだんだん認識し始めてきたようだ。
昨日の日経新聞いわく「日本は80兆円の直接投資を約束した。実際にお金を投じれば、円売りになり、為替相場への影響は避けられない」「これが本当に実行されれば、1ドル=200円では済まない円安水準になりますよ」。ある邦銀の為替ディーラーは神経をとがらせる」「ふくおかフィナンシャルグループの佐々木融チーフ・ストラテジストによれば、日本から米国に1兆円の投資フローが生じると、おおむね1円程度の円安・ドル高圧力になる」「第一生命経済研究所の熊野英生首席エコノミストは「巻き戻しのない円キャリー取引のようなイメージ」と説明する」「工場の増設や雇用の創出を通じて米景気の下支えにつながれば、一段とドル買い方向の材料として意識される。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB138BV0T10C25A8000000/
3.「市場の関心事は『日米金利差』から『トランプ関税で日本が約束した80兆円の影響』に」
円暴落の最大で最も強烈な理由は日銀の信用失墜であるが、短期の視点でも市場の関心事は「日米金利差」から「トランプ関税で日本が約束した80兆円の影響」に移っていくだろう。
昨日の日経新聞が書くように、「巻き戻しのない円キャリー取引のようなもの」でありこの要因だけで1ドル=200円くらいは行く」との予想が強まってくるのではないか?
3.「ハイパーインフレ(≒円の紙くず化)不可避」
毎日新聞は8月14日、「国債が増大すればするほど…」という記事で日本に警告を発している。
私が何十年も発してきた警告と同じ内容だが、マスコミもいよいよ本格的に警告を鳴らし始めた。
対処方法は日銀が新しい中央銀行に取って変わられざるをえないと私は思う。新しい法定通貨が発行されるということだ(=円は法定通貨ではなくなる=円の紙くず化)。円だけしか持っていない人には地獄である。
戦争がないとハイパーインフレは起きない、と以前は麻生前財務大臣もおっしゃっていたが、国会でしつこく追及していたら「戦争が無くても起こる」と修正された。
毎日新聞記事中に「戦争中は日銀も国債を購入するために紙幣を大量発行したことが原因だ」と書かれているが、まさにこれがハイパーインフレの原因である。
こういう経験から財政ファイナンスは世界中で禁止されているのに今の日銀は他国中央銀行に比べて異次元に紙幣を刷りまくった。
以下毎日新聞記事。
「国民の間では財政への不安もくすぶっていたが、大政翼賛会は全国の隣組に配った冊子で『国家の続く限り元金や利子を支払わないということは絶対にありません』と一蹴し、『銃後の協力は国債を買うこと』と迫った▲虚構は敗戦で崩れた。激しいインフレで国債の価値が大幅に目減りし、紙くず同然と化した。戦争中は日銀も国債を購入するために紙幣を大量発行したことが原因だ▲この結果、国が抱えていた巨額の借金は「国庫の観点からみるかぎり雲散霧消した」(大蔵省財政史室編「昭和財政史」)。政府が得をする一方、国債を買わされた国民は多大な損失を被った。理不尽な対応がまかり通ったのが昭和の借金財政だった▲今の国の借金残高は国内総生産(GDP)の2倍と戦時並みだ」
https://mainichi.jp/articles/20250814/ddm/001/070/105000c
4.「バブル期の再現、でも日銀は動けない」
本日の日経新聞1面の記事に「ゴルフ会員権の値上がりが鮮明だ。関東圏の平均価格は15年ぶりの高値を更新した」とある。
株は史上最高値、都心不動産価格も高騰、ゴルフ会員権も15年ぶり高値と1985年から90年の「狂乱経済」と言われたバブル再燃の様相だ。
狂乱経済になっても、当時のバブルは円が毎年30円から40円の高値更新をしていた(強烈なデフレ要因)ために消費者物価指数(CPI)は0.5%程度と非常に低かった。しかし今は逆に円安傾向。資産インフレによるものすごいCPI上昇が予想される。
それでも日銀は動けない。財務内容による自死、金融システムの崩壊を恐れるからだ。
次回以降の政策決定会合ででは、どんな屁理屈で利上げを回避するのか?日銀は既に物価のントロール能力を失っており、詰んでいる。新しい中央銀行の設立による中央銀行のとっかえ(=円が法定通貨でなくなる=円の紙くず化)は近い。ドルを買ってハイパーインフレ(=円が法定通貨で無くなる)に備えなければならない時間は刻々と無くなっている。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB01DD90R00C25A8000000/
5,「日銀が物価のために金利を引き上げられない理由」
本来の中央銀行の主たる利益は「通貨発行益」であり、それは「受取利息」―「支払い利息」である。令和6年度の日銀の受取利息は約2.09(兆円)で、支払利息は1.37兆円であり、何とかプラスだ。
これは政策金利の0.5%への引上げが今年の1月24日で令和6年度の期間中ずっと0.5%ではなかったからだ。
日銀当座預金の内、法定準備金を除く残高は約500兆円であるから、もし1年間0.5%の政策金利が継続すれば支払い金利額(補完制度預金制度利息)は2,5兆円にのおぼり既に「通貨発行損」はマイナスだ。
これ以上の金利上げは損のたれ流しにつながる。物価上昇を抑えようと、かなり金利を上げればとんでもない損の垂れ流しとなる。
政策金利を1%に上げれば、「2.09兆円マイナㇲ5兆円」で3兆円近くの通貨発行損の発生だ(注:受取利息は2.09兆円からは多少増えるだろう)
米国並みに4%、5%にでも上げれば異次元の規模の損の垂れ流しだ。
私の国会での質疑で黒田前総裁、若田部前副総裁、植田日銀総裁は「政策金利を上げれば受け取り利息も増える」とのごまかしで逃げを図っていたが、日銀の保有国債のほとんどは固定金利の長期債であり、満期が来て乗り換えるまでは、受取利息は増えない。
既にとんでもない額の債券の評価損、これも利上げで当然膨れ上がる。さらには大幅利上げをしていけば、株式市場は下落し、保有株式の評価益も霧散するだろう。金利を上げれば、日銀の信用失墜、圓尾信用失墜は明白である。
6.「中央銀行が保有してはいけないはず株式からの利益で何とか債務超過や損益計算書の赤字を逃れている日銀」
「株式のように価格のボラタイルなものを中央銀行は、通貨あの信用を守るために保有してはいけない」とは金融論の基本のキである。
他国中央銀行はその大原則を守っており、株を所有している中央銀行など日銀以外ない(スイスの中央銀行は金融政策以外の理由で株を保有しているが少額)
中央銀行が保有してはいけないはず株式からの利益で何とか債務超過や損益計算書の赤字を逃れている日銀。本業では大きな債務超過と損の垂れ流しながら馬券で儲けを何とか出している大企業のようなもの。
7・「ナンバープレートが6060の車が多かったテニス場」
昨日、本日と運動不足解消、かつ汗をかくためだけのテニス。老体だから1試合ずつで切り上げ。テニスコートも高齢者が多いために真夏は閑散としている。
昔は「6060」などというナンバープレートの車が多多みられたが最近は見ない。皆、歳とって無欲になっちゃったんかしらん?(「6060」は6ゲーム先取の試合で「6-0.6-0で勝つ」との強い意志の表れ)・