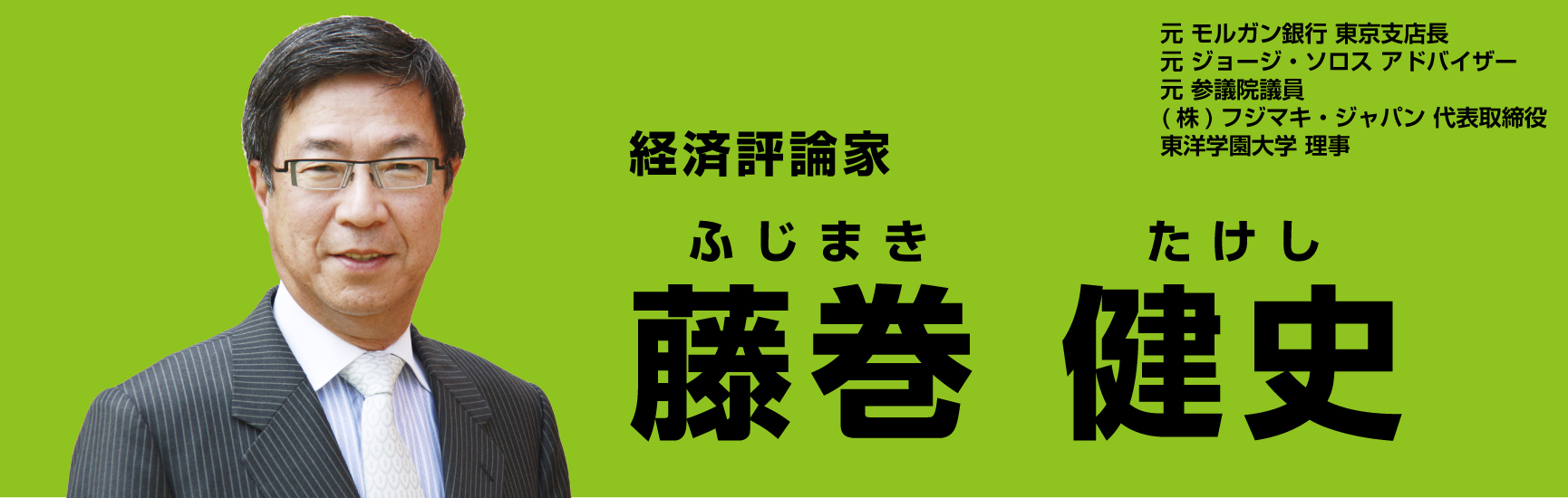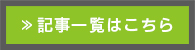1.「こりゃ、米国、強いわ」
「ブラックロックの幹部リーダー氏、次期FRB議長候補に急浮上-関係者」
昨日のブルムバーグニュース。
米資産運用大手ブラックロックの幹部リック・リーダー氏が、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の後任候補として有力視されつつあるそうだ。 「リーダー氏はブラックロックの最上級幹部の1人で、同社の債券ビジネスを統括している。2009年に同社に加わる前は、リーマン・ブラザーズに約20年勤務した」
「ベッセント氏はリーダー氏の長年にわたる市場でのキャリア、大規模組織の運営経験、経済に影響を与えるミクロ・マクロ要因に関する深い理解を高く評価している」
――>財務長官とFRB 議長が金融実務に長く携わったマーケットのプロ。
マーケット経験もない金融ド素人を参謀に据える日本の政権が金融/財政政策で大間違えするのは致し方ないか。
そもそも終身雇用制でジェネラリストを養成する日本の仕組みで米国のような市場のプロが出てくるかは疑問だが。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-09-12/T2HND6GP493C00?srnd=cojp-v2
2.「市場価格での国の超長期債バイバックは値段の下支えなどには全くならない」
9月11日の日経新聞記事。超長期債に国が買い戻しをするのではとの憶測が広まり、それが超長期債の価格を下支えしているというのだ。
しかし、これは単に超長期債を買いこんで途方に暮れている投資家の希望的観測か、もしくは少しでも高い値段で売り抜けたい人のためにする情報だろう。日経新聞が「ただ現時点では思惑が先行している状態」とあるとおりで無理筋の話だ。
バイバックをする場合、当然市場価格であるから、売った方は評価損が巨大な実現損となる。したがってバイバックに応じる機関投資家がいるかはおおいに疑問。
またまさか財務省が表面価格で買いとるなどバカなことをするわけはない。重大な責任問題となるからだ。
これは約束もしていなかったプットオプションをただで超長期債の買い手に与えることだ。買い手は大喜びであるが、国は大きな損失を被る。財務省の裁量で。私企業に利益を与え、国(しいては国民が)が損失を被るのは越権行為と指摘されてしまう。 これは予算行為であり、国会が、しかも発行前に判断すべき内容だ。よくわかっている財務省がそんなことをするはずがない。
ちなみに私が金融マン時代、国債の入札には額面価格でのバイバックをする可能性がありとの規定が入っていた。これは国がただでコールオプションを購入しているに等しい。国にとっては非常においしい条項である。購入者には不利益だが、その条件で入札に参加していたわけだから、まだ許される。
しかし、ある時、外国人から強烈なクレームが出た。これでは安心して入札に参加できないとのクレームだ。儲けていたと思ったら、突然その利益をはく奪されるからだ。
そこで入札の募集要項から、バイバック条項が消えた。しかし何度も言うように、これは入札の段階で、記載されていたことであり、それを承知で入札参加者が入札したのだから、まだ許される。
しかし、もし今回、額面価格で買い戻すのなら、入札の契約条項に書いてないのに突然、購入者にプットオプションの利益をただで与えることとなる。
金利上昇期にはなるべく低い固定金利で長く借金をすることはポートフォーリオの基本である。その理想的な資金調達をしていた国が無償でその権利を失うことになる。大問題となる。
したがって市場価格でのバイバックしか考えられないが、それが超長期債の価格維持につながるとは私には到底思えないのだ。
無理筋の話でマーケットを支えようとしているのなら、「もう終わり」の証拠。
3,「The International Economyに載った私の拙稿」
昨日紹介しましたThe International Economyに載った私の拙稿は最下部にあります。1ページ目の編集者の序説(雑誌本体ではp28)で
「A senior Japanese Banker suggested the Bank of Japan would go bankrupt and the yen would
lose its status as legal tender」
と少し私に触れてくれていています。
私の拙稿自体は6ページ目(雑誌本体ではp33)からp8(雑誌自体ではp36)までです。