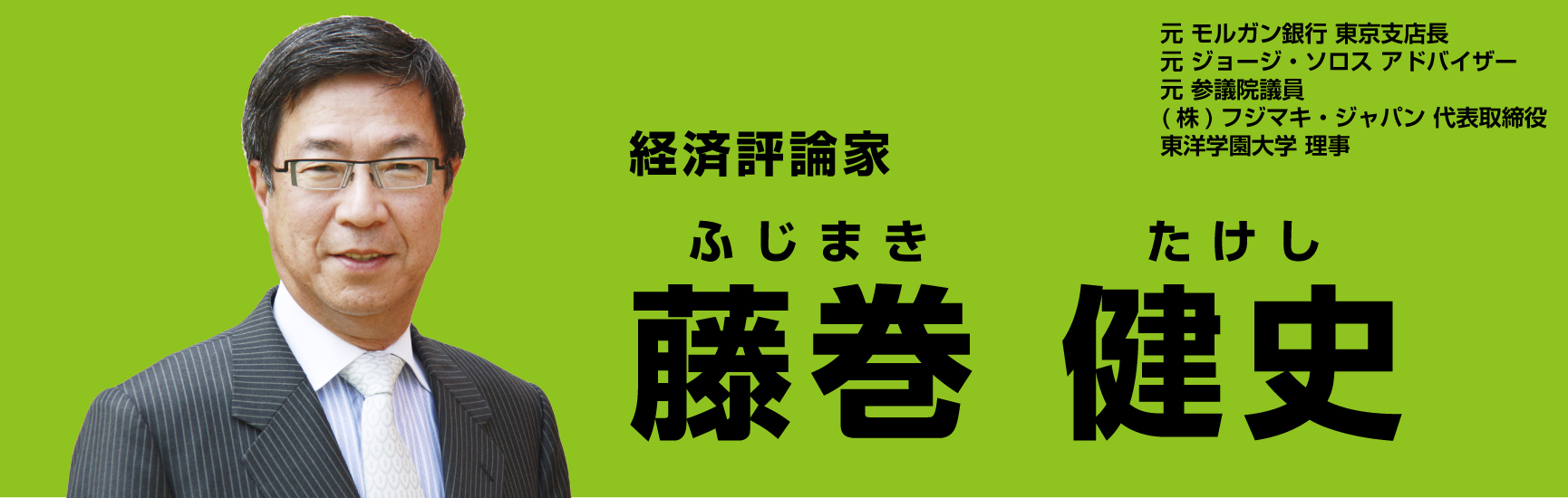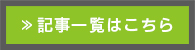1.「いよいよ切羽詰まってきたか」
住宅ローンを35年固定金利で借りている人が、今この時、変動金利型住宅ローンに変えようとするだろうか?まずそういう人はいないと思う。
財務省が今年度中に2四半期連続で超長期国債の発行減を決定するのは、その普通の人ならありえない行動だ・。
金利が上昇するなら、低いうちに長期固定のお金を借りるだけ借りるのが常識。金利上昇後は低い固定金利での長期間の資金調達は宝物だ。
ところが国は、この常識に逆行しようとしている。
国の利益を無視してまで、明日のため((金利上昇を防ぎたい)を求めるようでは、いよいよ、国も日銀も切羽詰まったなと思わざるを得ない。何はともあれ、今日、生き延びれることしか考えていない。金利が上昇したら、日銀はパンクだし、政府も予算を組めなくなってしまうからだ。
放漫財政と財政ファイナンスのツケはかくも重い。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA228ZM0S5A920C2000000/
2,「長期金利1.6%はまだまだ異常に低い」
前にも書いたが、債券先物(10年)は10年、6%クーポンの仮定債券を取引する。何故クーポンが6%かと言えば債券先物が出来た1985年当時は10年モノ金利とは6%が経験値だったからだ。
1989年の4月には11%を記録している。近年の日経平均ピークは本日の45,755円だが、それまでのピークは1998年12月の38,915円。この時の10年モノ金利は5.6%だった。
これらに比べて今の1.65%はあまりに低い。
学問的には名目金利は実質金利+期待インフレ率+(政府の)倒産確率で決まる。
実質金利ゼロ、政府の倒産確率ゼロと考えても名目金利の1.65%葉あまりに低い。
本来なら、今こそ20年債、30年債、40年債を山ほど発行するのが国益だ。しかし政府は逆のオペレーションをしている。これ以上、長期金利が上昇すると日銀も、中小金融機関も、弱小生保も生き延びられないからだ。情けなや。
しかし発行減額などでこの金利上昇は抑えきれるものではない。
放漫財政と財政ファイナンスのツケはかくも重い。
ちなみにこの期に超長期債の発行を増額するどころか減額すると、
名目金利=実質金利+期待インフレ率+(政府の)倒産確率で
(政府の)倒産確率が上昇し、中上記的には名目金利を押し上げることになろう。。
3.「米コロンビア大教授の伊藤隆敏氏」
たびたび日銀総裁や副総裁候補にあがった米コロンビア大教授の伊藤隆敏氏が亡くなったとのこと。合掌・
金融政策を巡る考え方はずいぶん異なったが尊敬はしていた。
同じ歳で私は東京教育大学附属高校で伊藤さんは東京教育大学駒場高校。高校2年の時、テニスの対校戦で、ダブルスで戦った。
テニスでは勝ったが受験では負けた。東大入試の無かった現役の時、伊藤さんは
一橋大学に現役入学、私はその年、一橋学院に入学。
同じ一橋でもえらい違い。なにせ一橋大学は大学で、一橋学院は予備校なんだから。安らかにお眠りください。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK249HE0U5A920C2000000/