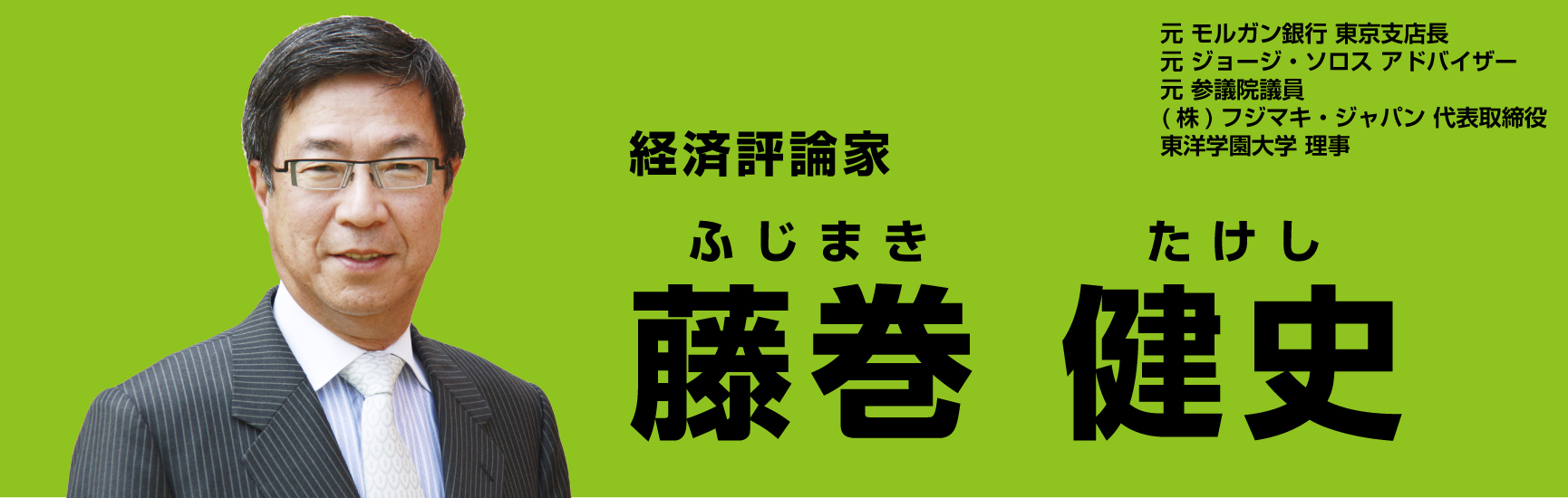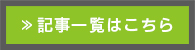1.「高市氏はサッチャー氏ではなく日本のトラス氏になる可能性もあるのでは?」
高市氏は元英国首相が理想だそうだが、財政・金融に関しての考え方は真逆。トラス元英首相に似ている。「尊敬する人はサッチャーよりトラスだった」と揶揄させないことを祈る。 今後のマーケットに備え、トラスショックを復習しておくことはとても重要だと思う。 2022年9月に英国トラス政権下で発表された大規模な減税・支出拡大策に対し、市場が反乱を起こした。トラスショックだ。長期金利急騰、通貨ポンドの急落、株式市場の急落が起きた。その結果、トラス首相は90日の歴代最短在職首相経験者となった。 英国10年金利は7月25日の1.88%からトラスショックで10月10日には4.32%まで上昇した。11月21日には3.11%まで反落したが、やはりそこが国債保有者にとっては最後の逃げ場だったようで現在は4.69%まで上昇している。 トラスショク直前の英国10年金利は現在の日本の10年金利より0.2%高い程度だったがトラスショックを経て現在は4.69%であること点は重要注意だ。 万が一、そこまで上昇すると、日本の生保、弱小金融機関、日銀は存在が難しくなるだろう。日銀の保有国債評価損は100兆円規模と天文学的に大きくなり、信用失墜、それに伴い円通貨の法定通貨としての地位失墜(=紙屑化)は不可避だ。 日本株も暴落だろう。 問題は日本の財務状態や日銀の財務内容は、放漫財政と財政ファイナンスにより。英国や英国中央銀行のそれより、比較にならないほど悪い点である。トランスショックなど起こらないと考えるのは楽観的過ぎる。
2.「高市氏が働いて、働いて、働き抜くほど日本は物価高、金利高、円安進行」
元日経新聞記者の磯野直之さんが以下のツイートをされていた。
「サッチャー元英首相は社会保障削減など小さな政府を徹底した。積極財政の高市氏とはかなり違う」
以下のようにリツイートした。
「これは非常に重要なポイント。私が邦銀のロンドン支店に転勤になった時は、フォークランド戦争の真っ最中でサッチャー時代だった。赴任直後のロンドンは地下鉄は動く灰皿、公衆電話の8割は壊れていて、ストが頻発し、しょっちゅう地下鉄は運休になり会社に行けず、清掃員のストで街は臭くてたまらなかった。それをサッチャーが変えた。日に日にロンドンが変わっていくのを見て、私は政治家1人の力でこんなに社会は変わるのかと驚いたものだ。そのサッチャーは磯野さんのおっしゃる通り小さな政府論者だった。4日の記者会見で積極財政を鮮明にした高市氏とは真逆の方針だ。高市氏は働いて、働いて、働いて、働き抜くそうだが高市氏が働けば働くほど、日本は物価高、金利高、円安が進むだろう。働かないほうがいいと思う」
3.「サッチャーの名言」
本日、以下のリツイートを私のX にいただいた。
.「国民の懐に手を突っ込んで、ばら撒きをする政治家は恥るべきがサッチャーさんが、おっしゃられることなので、そもそも自民党の考えと違いますよね?」
以下のように回答した。
「その通りですね。ただそれは自民党に限りませんが」。
4.「米銀のALM と日本の生保のALMとは真逆のコンセプト」
私が1985年にJPモルガンに転職した頃は、まだデリバティブも萌芽期で利益は、ALM (アセットライアビリティマネジメント)に多くの部分を頼っていた。ALMとは、資産と負債の期間をアンバランスにし、金利上昇期には短期で資金を運用し、長い期間の負債を調達する、金利下降期には、その逆。それをダイナミックに行って利益を確保することをALMと言っていた。邦銀も通常はイールドカーブが右上がりなので、ダイナミックではないもの当座預金や普通預金等の短期調達、長期運用で利益を確保していた。 ところが、生命保険業界に突然ALMとの概念が導入された。よく覚えていないが、生保が数多く倒産した後だったように思う。保険契約という長期の負債を抱えながら十分に長い資産を保有していないことが問題として、保有資産の長期化が進んだ。異次元緩和のせいで、著しく長期金利が低く抑えられていた(=価格が高い)長期の国債購入だから評価益は拡大していった。 米国で発展したコンセプトを導入したはずなのに.運用調達の期間をわざわざマッチングさせるとは本来のALMのコンセプトとは逆じゃないかと何度も書いたことがある。 日本の生保は日銀の国債爆買いによって長期金利が低下中(=価格上昇中)に国債を購入したから保有国債に巨大な評価益が出ていた。 しかし、それは長期金利が上昇すれば、とんでもない評価損が生じることを意味する。本来ALMというならば負債サイドも時価評価しなければならないが、保険会社の負債サイドは顧客に売った保険契約であり、その時価評価はなかなか難しい。 ただ、言える事は長期金利上昇期とはインフレ期である。インフレ率に劣る保険契約は解約されてしまうリスクが生じる。したがって、資産と負債のデュレーションを等しくさせるとのマネジメントでは金利上昇期に生命保険会社の経営は苦しくなる。現在は保有株式の評価益で何とかなっているかもしれないが株価が下落すれば大問題。9月末の中間決算発表は注目点。 何はともあれ、ある程度自己責任であったとは言え、異次元緩和でべらぼうに低く抑えられた金利の国債を大量に買わされた保険会社もいい迷惑だった。財政ファイナンスをつけば大きい。
5.「メガバンクは長期債を何故、日銀に売りつけることが出来たのか」
昨日、以下のリツイートを私のX にいただいた。
「メガバンクが長期債を日銀に売りつけられたことがなぜできたのか?なぜ中小銀行が長期債をそんなに持っているのか?わかりません」
以下のように回答した。
「財政論、金融論を理解していなければ、メガバンクの幹部など務まらない。理解していれば異次元化を続ければ、長期国債の保有が危なくなる事は常識。日銀が異次元緩和をするために長期債をどんどん買いますと言うのだから大規模な売却はいとも簡単。日銀の爆買いの時だから長期金利は低下中(=価格上昇)。したがって保有国債売却で利益確保にもなった。